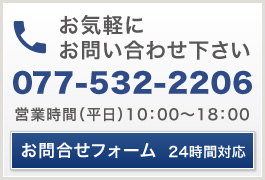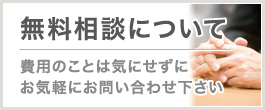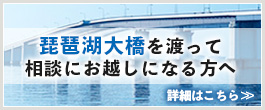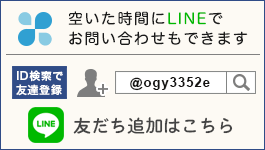Author Archive
国際結婚 その1 外国人と日本で結婚する場合の法律関係
国際結婚 その1 外国人と日本で結婚する場合の法律関係
国際結婚をする場合に、日本の法律と外国の法律のどちらが適用されるのでしょうか?
日本人が外国人と国際結婚をする場合、日本と相手国のそれぞれの法律が適用されます。
日本には民法によって結婚できる条件が定められていますが、
これは日本だけの条件で、他の国々では結婚できる条件がそれぞれ異なっています。
そのため、これから国際結婚をする方々は、まず、それぞれ相手国の結婚に関する法律を
調べて知ることが必要になります。
【婚姻の成立は、それぞれの本国法にしたがって決める】
日本人と外国人が国際結婚をする場合、
婚姻の成立は、各当事者につき、その本国法にしたがって決めます。
そのため、日本人は民法、外国人は外国人の本国法で結婚に関する条件を
確認することになります。
日本人の方は、民法によって、結婚に関する条件を確認します。
民法の条件は以下のとおりです。 ※ 平成28年8月現在
・男性は満18歳以上、女性は満16歳以上であることが必要です。
・すでに配偶者のある者とは重ねて婚姻をすることができません。
・女性は、前婚の解消、または取消しの日から6ヶ月を経過した後でなければ、
再婚をすることができません。
・直系血族または三親等以内の傍系血族同士の間では、婚姻をすることができません。
・直系姻族間の婚姻はできません。
・養親子間の婚姻はできません。
・未成年者は父母の同意を得なければ婚姻できません。
外国人の方についての結婚に関する条件は、その外国人の母国の法律で確認しますが、
日本の民法の条件である近親婚でないこと、重婚でないこと、再婚禁止期間でないこと等は、
相手の外国人にも影響します。
これらの民法の条件は、日本人と外国人の双方が条件を満たしている必要がある双方的要件と
されているため、日本人と外国人の双方が条件を満たす必要があります。
【国際結婚の成立まとめ】
日本人と外国人の国際結婚の成立のためには、
まず、日本人と外国人のそれぞれが母国の法律の条件を満たしている必要があります。
そして、さらに、お互いに相手国の双方的要件も満たしている必要があるということです。

離婚協議書や遺言書の作成といった暮らしに密着した法務から、帰化申請などの国際業務、ドローンの飛行許可申請といった最新の許認可まで、幅広く対応しております。「身近な法律家」として、皆様のお困りごとを解決に導くお手伝いをいたします。
初回無料相談受付。事前予約で平日夜間や休日のご相談にも対応可能です。また、ご希望に応じて出張相談にも対応できます。対応地域は滋賀県全域、大阪・京都など。他府県の方からのご相談も承っております。まずはお気軽にお問い合わせください。
遺言書と再婚 再婚は相続争いが起こりやすいケース
遺言書と再婚 再婚は相続争いが起こりやすいケース
離婚・再婚は相続争いが起こりやすいケースです。
なぜなら、相続に関係する登場人物が多く、その相続人間の感情の対立もあり、
相続財産を分割する話合いがまとまりにくいことがその理由です。
その登場人物とは・・・、
離婚した前の配偶者とその間に生まれた子、再婚した配偶者とその間に生まれ子、
さらに、再婚した配偶者の連れ子を養子にしているケースもありえます。
このように、離婚歴や再婚歴がある方は、将来、相続争いが起こりやすくなりますが、
遺言書による対策によって、その争いを予防することができます。
【再婚の場合、法定相続人はどうなるの!?】
離婚した元配偶者は相続人にはなりません。
相続人となるのは再婚した配偶者とその間に生まれた子、離婚した配偶者との間の子です。
相続分の割合は、再婚した配偶者が相続財産の1/2を相続します。
そして、再婚した配偶者との間に生まれた子、離婚した配偶者との間の子で
相続財産の1/2を相続します。
そのため、再婚した配偶者とその間に生まれた子、離婚した配偶者との間の子が
相続財産をどのように分けるのかを話合う必要があります。
このような場合に円滑な話合いができるでしょうか?
また、再婚した配偶者の連れ子を養子にしている場合はどうでしょうか?
多くの場合、それぞれの立場による感情の対立によって、話し合いがうまくいかず、
紛争になる可能性が高いです。
離婚した配偶者との間の子からすると、新たに再婚した配偶者との間の子がいることは、
あまり気持ちがよいものではありません。
また、自身の親が再婚した配偶者の連れ子を養子にした場合も同様です。
【遺言書による対策が効果的】
離婚・再婚の経験がある方は、相続が発生した時に紛争になる可能性がありますので、
遺された相続人のためにも遺言書による対策をすることをお勧めします。
具体的には、各相続人の遺留分に配慮したうえで、「相続させる」という文言を使用して、
可能な限り、財産の分配を指定して、遺産分割協議の余地を無くす遺言書を作成することが
良いのではないでしょうか。
また、財産の配分と同時にその理由を遺言書に記載することでトラブルを予防することも
できます。

離婚協議書や遺言書の作成といった暮らしに密着した法務から、帰化申請などの国際業務、ドローンの飛行許可申請といった最新の許認可まで、幅広く対応しております。「身近な法律家」として、皆様のお困りごとを解決に導くお手伝いをいたします。
初回無料相談受付。事前予約で平日夜間や休日のご相談にも対応可能です。また、ご希望に応じて出張相談にも対応できます。対応地域は滋賀県全域、大阪・京都など。他府県の方からのご相談も承っております。まずはお気軽にお問い合わせください。
子どもがいない夫婦に遺言書は必要なのか その2
子どもがいない夫婦に遺言書は必要なのか その2
それでは、前回からの続きです。
【代襲相続により甥・姪が相続人となる場合には、さらに厄介なことに・・・。】
子どもがいない夫婦のどちらかが先に亡くなり、亡くなった配偶者の兄弟姉妹に相続権が
ある場合で、さらに、その兄弟姉妹の子である甥・姪が兄弟姉妹の相続権を引き継ぐ、
代襲相続が起こると厄介なことになります。
代襲相続により、甥・姪が相続権をもった場合、その甥や姪と相続財産についての
遺産分割協議が必要になるからです。
そのような相続人と遺産分割協議をすることは遺された配偶者にとって、
相当の負担があるといえます。
【子どもがいない夫婦の一方が先に亡くなった場合の相続人まとめ】
子どもがいない夫婦のどちらかが先に亡くなった場合、一般的に相続人となる可能性が
あるのは、遺された配偶者と亡くなった配偶者の父母・兄弟姉妹・甥姪のいずれかです。
このような場合に、遺された配偶者は亡くなった配偶者の父母・兄弟姉妹・甥姪の
いずれかと相続財産についての遺産分割協議をする必要があります。
現実的に多くあるのは、亡くなった配偶者の兄弟姉妹や甥姪と遺産分割協議をする場合です。
普段から亡くなった配偶者の兄弟姉妹や甥姪と面識は多くないでしょうし、
そのような相続人と遺産分割協議をすることは遺された配偶者にとって、
相当の負担があるといえます。
【遺言書による対策はどうする!?】
子どもがいない夫婦のどちらかが先に亡くなったときに、現実によくあるケースとしては、
亡くなった配偶者の父母はすでに亡くなっていて、その兄弟姉妹や甥姪が相続人となる場合です。
このようなケースにおける遺言書による対策ですが、
「すべての財産を配偶者の○○○に相続させる」という遺言書を作成することで、
兄弟姉妹や甥姪には相続権がなくなり、すべての財産を確定的に遺された配偶者に残すことが
できるようになります。
通常、相続人には最低限保障された相続分である遺留分がありますが、
兄弟姉妹や甥姪には遺留分がないため、遺言書による対策が非常に効果的です。
ポイントは、「兄弟姉妹や甥姪には遺留分がない」ということです。
遺留分がないため、遺言書で財産を自由に分配することができます。
もちろん、遺された配偶者にすべての財産を相続させることもできますし、
そのほかの分配についても自由にできます。
例えば、
子どもがいない夫婦のどちらかが先に亡くなったときに、遺された配偶者の生活のために
すべての財産を残すことを希望する場合には、遺言書による対策によって実現できます。
子どもがいない夫婦は、夫婦のどちらが先に亡くなるのかわかりませんから、
夫婦のそれぞれが遺言書を作成しておくことをお勧めします。
そして、その後、一方の配偶者が亡くなられ、遺言書のとおりに相続財産を相続した後、
遺された配偶者はその時点でその時の状況に合わせて遺言書を再度作成しなおすことを
お勧めします。

離婚協議書や遺言書の作成といった暮らしに密着した法務から、帰化申請などの国際業務、ドローンの飛行許可申請といった最新の許認可まで、幅広く対応しております。「身近な法律家」として、皆様のお困りごとを解決に導くお手伝いをいたします。
初回無料相談受付。事前予約で平日夜間や休日のご相談にも対応可能です。また、ご希望に応じて出張相談にも対応できます。対応地域は滋賀県全域、大阪・京都など。他府県の方からのご相談も承っております。まずはお気軽にお問い合わせください。
子どもがいない夫婦に遺言書は必要なのか その1
子どもがいない夫婦に遺言書は必要なのか その1
子どもがいない夫婦の一方が亡くなった場合、危険な紛争になる可能性があります。
有効な対策がなければ、遺された配偶者はたいへん頭を悩まされることでしょう。
【子どもがいない夫婦の一方が亡くなった場合の相続人は誰!?】
子どもがいない夫婦の一方が先に亡くなった場合、全ての財産を配偶者が相続するとは
限りません。よく誤解のあるところですから注意が必要です。
それでは、子どもがいない夫婦の一方が亡くなった場合の相続人を確認しましよう。
まず、配偶者は常に相続人となります。
※配偶者とは、法律上の婚姻関係にある配偶者のことで、内縁関係の者、愛人関係の者、
離婚した元配偶者などは、相続人ではありません。
そして、その他にも相続人がいます。
それは、亡くなった配偶者の父母です。その父母がすでに亡くなっている場合であれば、
亡くなった配偶者の兄弟姉妹が相続人になります。
それぞれのケースの相続分の割合は、以下のとおりです。
遺された配偶者 2/3 亡くなった配偶者の父母 1/3
遺された配偶者 3/4 亡くなった配偶者の父母 1/4
【遺された配偶者には負担のかかる相続財産の話合い】
子どもがいない夫婦のどちらかが先に亡くなったら、すべての財産を遺された配偶者が
相続するものと誤解しがちですが、法律は、亡くなった配偶者の父母、そして、その父母が
すでに亡くなっている場合であれば、亡くなった配偶者の兄弟姉妹に相続権を認めています。
そのため、先に亡くなった配偶者に父母あるいは兄弟姉妹がいる場合には、
遺された配偶者は亡くなった配偶者の父母あるいは兄弟姉妹と相続財産についての
話合いが必要になります。
このように、子どもがいない夫婦のどちらかが先に亡くなった場合、
遺された配偶者は亡くなった配偶者の父母あるいは兄弟姉妹とどのように
相続財産を分けるのかといった遺産分割協議が必要になります。
また、亡くなった配偶者名義の預貯金を解約して払い戻しを受ける場合にも、
金融機関からは相続人全員の承諾を求められることになります。
これまでの義理の父母や兄弟姉妹との関係がよくなければ、遺された配偶者にとっては、
相当の負担になるでしょう。仮に、義理の父母や兄弟姉妹との関係がよかったとしても、
やはり、お金の話合いですから、遺された配偶者にとっては相当の負担となるでしょう。
それでは、次回に続きます。
次回は、さらに厄介になる義理の兄弟姉妹に代襲相続が発生するケースもご紹介します。
そして、遺言書による対策をお伝えします。

離婚協議書や遺言書の作成といった暮らしに密着した法務から、帰化申請などの国際業務、ドローンの飛行許可申請といった最新の許認可まで、幅広く対応しております。「身近な法律家」として、皆様のお困りごとを解決に導くお手伝いをいたします。
初回無料相談受付。事前予約で平日夜間や休日のご相談にも対応可能です。また、ご希望に応じて出張相談にも対応できます。対応地域は滋賀県全域、大阪・京都など。他府県の方からのご相談も承っております。まずはお気軽にお問い合わせください。
帰化が許可された後の手続を忘れずに
帰化が許可された後の手続を忘れずに
帰化が無事に許可された後にも一定の手続きが必要になります。
忘れずに手続きを済ませましょう。
【その1 法務局から「帰化者の身分証明書」が交付される】
帰化が許可されるとその旨が官報に告示され、法務局から「帰化者の身分証明書」が
交付されます。
【その2 帰化の届出を市町村役場へ届ける】
現居住地または新たに定めた本籍地の市町村役場に「帰化届」と「帰化者の身分証明書」を
提出します。これにより、日本の戸籍が作成されます。
なお、帰化が許可されてから1ヶ月以内に帰化届を提出する必要があります。
【その3 在留カード・特別永住者証明書等を入国管理局へ返納する】
帰化者の居住地を管轄する入国管理局へ在留カード・特別永住者証明書を返納します。
【その他の手続き】
帰化者の事情に応じて必要となる手続きをする必要があります。
その他の手続きは、以下に記載されている事項の他にも帰化者の事情に応じて必要となる
手続きがありますので、ご注意ください。
・国籍離脱の手続き
・日本のパスポートの申請
・運転免許証の氏名等の変更手続き
・保険・年金の名義変更
・銀行口座の名義変更
・不動産登記の名義変更
・営業許可証等の名義変更 ・・・etc.

離婚協議書や遺言書の作成といった暮らしに密着した法務から、帰化申請などの国際業務、ドローンの飛行許可申請といった最新の許認可まで、幅広く対応しております。「身近な法律家」として、皆様のお困りごとを解決に導くお手伝いをいたします。
初回無料相談受付。事前予約で平日夜間や休日のご相談にも対応可能です。また、ご希望に応じて出張相談にも対応できます。対応地域は滋賀県全域、大阪・京都など。他府県の方からのご相談も承っております。まずはお気軽にお問い合わせください。
帰化申請と永住許可どちらを選ぶ!? それぞれのメリットを比較
帰化申請と永住許可どちらを選ぶ!? それぞれのメリットを比較
「帰化と永住、どちらを選択するべきでしょうか?」と質問をいただくことがあります。
帰化申請をして日本人になるのか、外国人のまま永住権を取得するのかどうかは、
国籍に関する選択ですから、非常に悩ましい問題です。
生涯日本で住み続ける意志があるのなら、帰化を申請して日本の国籍を取得することを
お勧めしますが、将来母国に帰る可能性のある場合や母国に対する愛情がある場合には、
現時点では永住権の取得にとどめておき、ご自身の中で決心がついた時点で帰化申請を
することをお勧めします。
以下、帰化と永住権の比較になります。
【帰化のメリット・デメリット】
・帰化すれば日本国籍をもつことができ、日本人と同じになります。
・日本の選挙権・被選挙権が与えられます。
・戸籍をもつことができます。
・日本のパスポートは外国への観光や商用にとても便利です。
・外国人登録カードの所持義務が無くなります。
・入国管理局の手続きがなくなります。
・再入国の手続きが不要になります。
・強制退去の対象とはなりません。
・母国の国籍を失います。
・帰化のためには、ある程度の日本語能力が必要です。
【永住権のメリット・デメリット】
・日本にずっと居住することができ、在留期間の更新手続がなくなります。
・母国の国籍を失いません。
・永住者の配偶者や子は他の一般在留者の場合より簡易な基準で永住許可が取得できます。
・職業に制限がなくなり、自由に職業の選択ができます。
・銀行・公庫などの住宅ローンなどが利用できます。
・再入国の手続きは必要です。
・強制退去の対象となります。

離婚協議書や遺言書の作成といった暮らしに密着した法務から、帰化申請などの国際業務、ドローンの飛行許可申請といった最新の許認可まで、幅広く対応しております。「身近な法律家」として、皆様のお困りごとを解決に導くお手伝いをいたします。
初回無料相談受付。事前予約で平日夜間や休日のご相談にも対応可能です。また、ご希望に応じて出張相談にも対応できます。対応地域は滋賀県全域、大阪・京都など。他府県の方からのご相談も承っております。まずはお気軽にお問い合わせください。
帰化は3種類ある!? 帰化の種類を知ろう
帰化は3種類ある!? 帰化の種類を知ろう
帰化とは、外国人が日本国籍を取得することです。
在日韓国・朝鮮人の方々や日本人と結婚した外国人、日本で就労している外国人の方の
多くが日本国籍の取得を希望して帰化申請をしています。
外国人の方が日本人になるためには、帰化をする必要があって、その手続が帰化申請です。
帰化には3種類があることをご存知ですか?
帰化は、国籍法で、普通帰化、簡易帰化、大帰化の3種類が規定されています。
普通帰化について
普通帰化の対象となるのは、外国で生まれて、その後、日本に来て、日本で
就職をしているといった一般的な外国人の方です。
普通帰化の要件は、住居要件、能力要件、素行要件、生計要件、喪失要件、思想要件、
日本語能力要件の7つあります。
簡易帰化について
帰化の種類の中には、帰化の要件が緩和されている簡易帰化というものがあります。
典型的な簡易帰化の要件にあてはまるのは、在日韓国人・朝鮮人(特別永住者)の方々、
日本人と結婚している外国人の方々です。
そのため、特別永住者と日本人と結婚している外国人は帰化が認められやすくなります。
簡易帰化は、普通帰化の7つの要件が緩和または免除されています。
帰化の要件が緩和・免除されているので簡易帰化と呼んでいます。
【在日韓国人・朝鮮人の方々の多くがあれはまる国籍法6条】
・日本で生まれたもので引き続き3年以上日本に住所若しくは居所を有し、又は
その父若しくは母が日本で生まれたもの。
日本で生まれた在日韓国人・朝鮮人の方々の多くがこのケースにあたります。
【日本人と結婚している外国人の多くがあれはまる国籍法7条】
・日本国民の配偶者たる外国人で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、
現に日本に住所を有するもの。
外国人の方が、すでに、日本に3年以上住んでいるなら、日本人と結婚した時点で
この要件を満たします。
・日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上
日本に住所を有するもの。
外国で結婚し、その結婚生活が3年を経過していれば、その後、来日して日本に1年以上
住んでいる場合にこの要件を満たします。
このように、在日韓国人・朝鮮人(特別永住者)の方々、日本人と結婚している外国人の
方々は、帰化の要件が緩和されていて、帰化が認められやすくなっています。
大帰化について
日本に対して特別に功労実績のある外国人に許可されるのが大帰化です。
いまだ、大帰化が許可された前例はありません。

離婚協議書や遺言書の作成といった暮らしに密着した法務から、帰化申請などの国際業務、ドローンの飛行許可申請といった最新の許認可まで、幅広く対応しております。「身近な法律家」として、皆様のお困りごとを解決に導くお手伝いをいたします。
初回無料相談受付。事前予約で平日夜間や休日のご相談にも対応可能です。また、ご希望に応じて出張相談にも対応できます。対応地域は滋賀県全域、大阪・京都など。他府県の方からのご相談も承っております。まずはお気軽にお問い合わせください。
性格の不一致(価値観の相違)と慰謝料
性格の不一致(価値観の相違)と慰謝料
離婚の慰謝料とは、相手方の有責行為(不倫・暴力等)によって、離婚にいたった場合に、
その精神的苦痛をつぐなうことを目的として支払われるものです。
離婚すれば、必ず慰謝料が発生すると考えている方が多いですが、そうではありません。
慰謝料の問題が発生するのは、相手方の有責行為(不倫・暴力等)があった場合です。
そのため、夫婦のどちらにも責任がない場合には慰謝料の問題は起こりません。
また、夫婦のどちらにも責任がある場合も慰謝料の問題は起こりません。
このように、離婚の慰謝料はどちらが離婚原因をつくったのかが問題になります。
では、離婚原因で一番多い「性格の不一致」についてはどうでしょうか?
「性格の違い」、「価値観の違い」については、よほどのことがなければ慰謝料を
支払わなければならないほどの有責性があるとは言い難いです。
そのため、夫婦の性格の不一致や価値観の相違が原因で離婚にいたったとしても、
そのことを理由に慰謝料を請求することは、現実的には困難なケースがほとんどです。
そもそも、人が生まれながらもつ性格は様々で、それは個性でもありますから、
一方的に非難することは相当ではないからです。
【性格の不一致(価値観の相違)と慰謝料のまとめ】
仮に、夫婦間の性格の不一致(価値観の相違)が民法の「婚姻を継続し難い重大な事由」に
該当したとしても、性格の不一致といえども、その責任が夫婦のどちらか一方にあるとは
言い難く、慰謝料を請求することは現実的には困難なケースが多いです。

離婚協議書や遺言書の作成といった暮らしに密着した法務から、帰化申請などの国際業務、ドローンの飛行許可申請といった最新の許認可まで、幅広く対応しております。「身近な法律家」として、皆様のお困りごとを解決に導くお手伝いをいたします。
初回無料相談受付。事前予約で平日夜間や休日のご相談にも対応可能です。また、ご希望に応じて出張相談にも対応できます。対応地域は滋賀県全域、大阪・京都など。他府県の方からのご相談も承っております。まずはお気軽にお問い合わせください。
約束を守らせる公正証書の心理的圧力
約束を守らせる公正証書の心理的圧力
それでは、前回からの続きです。
前回は、公正証書の債務名義としての効力 をお伝えしました。
今回は、 その3 公正証書の心理的圧力としての効力 を説明します。
これまでのコラムの内容のとおり、公正証書には優れた証拠としての効力があって、
さらに、お金の支払いを守らない者に対して強制執行ができる債務名義としての効力が
あることをお伝えしてきました。
そのため、公正証書を作成した相手方(債務者)に対して、
公正証書で約束した内容を守らなければならないという無言の圧力がかかります。
なぜなら、公正証書のお金の支払いに関する約束に違反すれば、ただちに強制執行されて
しまうからです。また、公正証書は裁判での有力な証拠となり、相手方としても争うのに
困難を覚えますから、やはり、できるだけ約束を守ろうということになります。
このように、公正証書の心理的圧力とは、公正証書の約束を守らなければならないという
無言の圧力がかかることです。この無言の圧力が相手方に与える影響が強いため、
相手方は公正証書で約束した内容をしっかり守ろうという気持ちになります。
例えば、あなたがお金を請求する立場であれば、相手方が約束を守らない場合には、
「お金を支払え」とずっと催促しつづける必要があります。
これは、非常に面倒で、お金を請求するあなたにとってもストレスがかかることです。
ですが、公正証書があれば、相手方には無言の圧力が強くかかっていますので、
あなたが催告をしつづけるという面倒なことをしなくても、任意にお金を支払ってくれる
でしょう。
それも、その効果はお金の支払が終わるまで、ずっと続いていきます。
このような公正証書の心理的圧力は、慰謝料の分割支払い、養育費の支払いといった、
長期にわたる支払い義務のある相手方に対して非常に有効だと思いませんか?
公正証書の優れた3つの効力まとめ
・証拠としての効力
・債務名義としての効力
・心理的圧力としての効力
以上のことから、
公正証書は、お金の支払いに関する約束には非常に有効な手段だといえます。

離婚協議書や遺言書の作成といった暮らしに密着した法務から、帰化申請などの国際業務、ドローンの飛行許可申請といった最新の許認可まで、幅広く対応しております。「身近な法律家」として、皆様のお困りごとを解決に導くお手伝いをいたします。
初回無料相談受付。事前予約で平日夜間や休日のご相談にも対応可能です。また、ご希望に応じて出張相談にも対応できます。対応地域は滋賀県全域、大阪・京都など。他府県の方からのご相談も承っております。まずはお気軽にお問い合わせください。
養育費、慰謝料、財産分与の約束には必須の債務名義としての効力
養育費、慰謝料、財産分与の約束には必須の債務名義としての効力
それでは、前回からの続きです。
前回は、公正証書の証拠としての効力をお伝えしました。
今回は、 その2 公正証書の債務名義としての効力 を説明します。
債務名義ってむずかしい言葉ですよね!?
できるだけ簡単に説明しますので、読み進めてみてください。
債務名義とは、「強制執行をすることが認められている文書」のことです。
つまり、強制執行ができる公正証書を作成したなら、その公正証書を債務名義と呼びます。
どうでしょうか? なんとなく、ご理解いただけたでしょうか?
「強制執行ができる文書を債務名義と呼ぶ」 ということですね。
公正証書は、一定の要件を満たして作成すれば、ただちに強制執行ができます。
そのため、公正証書は、お金の支払いに関する約束をするのに優れています。
離婚に関する公正証書の場合は、養育費、慰謝料、財産分与といった離婚後のお金を支払う
約束を守ってもらう為によく利用されています。
ふつうは、強制執行をするためには、裁判で勝訴することが必要ですが、
一定の要件を満たして公正証書を作成すれば、裁判をすることなく、
ただちに、強制執行ができます。
なんと、裁判をしなくてもよいのです。 これは非常に助かりますよね。
なぜなら、裁判をするためには、相当の費用を負担する必要があるのですから。
この債務名義としての効力があるから、公正証書はよく利用されています。
このように、公正証書が最も利用される理由は、
ただちに、強制執行ができるという債務名義としての効力があるからというわけです。
この「公正証書の債務名義としての効力」は、離婚後の養育費、慰謝料、財産分与といった
お金を支払う約束をするにあたって、すごく役に立つと思いませんか?
それでは、次回に続きます。
次回は、「その3 公正証書の心理的圧力としての効力」です。

離婚協議書や遺言書の作成といった暮らしに密着した法務から、帰化申請などの国際業務、ドローンの飛行許可申請といった最新の許認可まで、幅広く対応しております。「身近な法律家」として、皆様のお困りごとを解決に導くお手伝いをいたします。
初回無料相談受付。事前予約で平日夜間や休日のご相談にも対応可能です。また、ご希望に応じて出張相談にも対応できます。対応地域は滋賀県全域、大阪・京都など。他府県の方からのご相談も承っております。まずはお気軽にお問い合わせください。