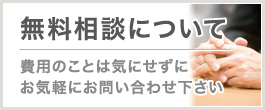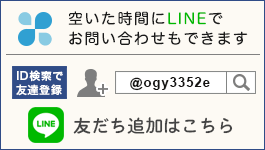遺言書作成の注意点
遺言書を作成するには法律的に注意するべきことがたくさんあります。
遺留分、遺留分減殺請求権、特定遺贈、包括遺贈、負担付遺贈、特別受益の持戻し、特別受益の持戻し免除、「相続させる」と「遺贈する」の差異、遺言書の検認手続き、遺言書の保管、遺言執行者、付言事項・・・、
このように、法律的に注意すべきことはキリがありません。
遺言書を残す遺言者の個別具体的な事情に応じて対応するしかありません。
遺言者の希望する遺言書の内容をお伺いしたうえで、その希望する遺言書を作成するために、注意すべき点を見極めて、最善の選択をするということです。
遺言書作成の注意点 その1 必ず理解しよう、遺留分と遺留分減殺請求権
遺留分制度とは、一定の相続人に最低限の相続財産を保障する制度です。
財産を残す遺言者の立場からすると、全ての財産を自由に処分することはできず、遺留分の割合だけは一定の相続人へ残す必要があるということです。
一方、財産を受け取る相続人の立場からすると、最低限保証された相続分があるということになります。
そして、その遺留分の権利を保証された一定の相続人のことを遺留分権利者と言います。
民法では、遺留分権利者を「兄弟姉妹以外の相続人」と規定しています。
具体的に、遺言者の立場からすると、配偶者・子または子の代襲相続人・直系尊属です。
そんな遺留分権利者は最低限保証された相続分がありますから、相続によって取得した相続財産が遺留分に満たない場合は、「遺留分を侵害された」として、侵害された遺留分を取り戻す権利があります。
その権利を、遺留分減殺請求権と言います。
そのため、遺言書を作成するにあたっては、遺留分・遺留分権利者・遺留分減殺請求権といったものを考慮して遺言書の内容を検討する必要があります。
もし、遺言書の内容が遺留分を侵害する場合、その遺留分を侵害された遺留分権利者から、遺留分減殺請求権が行使される可能性があります。
その場合、遺言書の内容が実現することができない事態となってしまいます。
遺留分を侵害する遺言書を作成してしまうことのないように、注意する必要があります。
遺言書作成の注意点 その2 遺贈は複雑です
遺贈とは、遺言者が遺言によって財産を希望する者へ贈与することです。
遺言者は、遺留分に反しない範囲で、自由に財産を遺贈することができます。
遺贈には、財産のうちの割合のみを示して贈与する包括遺贈と、財産を特定して贈与する特定遺贈があります。
そして、遺贈を受ける者のことを受遺者と呼びます。
遺言書に遺贈に関する内容を記載する場合には、法律的に注意すべき点があります。
それは、民法は、
「遺贈が、その効力を生じないとき、又は放棄によってその効力を失ったときは、受遺者が受けるべきであったものは、相続人に帰属する。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う」と規定しています。
そのため、遺贈を遺言書の内容とする場合には、遺贈が効力を生じないとき・遺贈が放棄によって効力を失ったときに備えて、遺言者の意思を遺言書に記載しておくことまで考えて、遺贈に関する内容を検討する必要があります。
つまり、遺贈をすることばかりに注意するのではなくて、その遺贈が効力を生じないとき・遺贈が放棄によって効力を失ったときのことまで、しっかり考慮した上で、遺言書の内容を決定する必要があります。
それから、民法は、
「包括遺贈を受けた受遺者は、相続人と同じ権利義務を持つことになる」と規定しています。
そのため、包括遺贈では、相続人と同様に、積極財産・消極財産の双方をその割合に応じて承継することになります。
つまり、包括遺贈は、マイナスの負債もその割合に応じて承継することになります。
もし、プラスの財産だけを遺贈したいのであれば、特定遺贈を選択するべきです。
さらに、包括遺贈は財産のうちの割合のみを示すものなので、包括遺贈を受けた受遺者は、相続人全員と、別途、遺産分割協議をしなければなりません。
そのため、相続人以外の第3者に遺贈を検討しているのであれば、包括遺贈にするよりも、その後のトラブル回避のために特定遺贈にすることをお勧めします。
遺言書作成の注意点 その3 負担付遺贈はバランスに注意
負担付遺贈とは、遺言者が遺贈によって財産を贈与する代わりに、一定の法律上の義務を負担させるという遺贈の種類です。
その負担付の遺贈を受け取った者は、財産を得る代わりに、負担も負うことになります。
負担付遺贈の具体例は次の通りです。
- 遺言者の配偶者を相続人の一人に世話・介護させる代わりに、一定の財産を遺贈する場合。
- 遺言者のペットの世話をさせる代わりに、一定の財産を遺贈する場合。
- 障害のある遺言者の子の扶養を負担させる代わりに、一定の財産を遺贈する場合。
このような、負担付遺贈ですが、遺言書の内容とする場合には注意点があります。
それは、民法が、
「負担付遺贈を受けた受遺者は、遺贈された目的の価値を超えない限度においてのみ負担した義務を履行する責任を負う」と規定していることから、負担付遺贈は、負担と遺贈する財産とのバランスが大切であることがわかります。
そして、民法は、
「受遺者が負担付遺贈の放棄をしたときは、負担の利益を受けるべき者は、自ら受遺者となることができる。ただし、遺言者が別段の意思を表示したときはその意思に従う」と規定しています。
そのため、負担付遺贈については、負担と遺贈する財産とのバランスが悪ければ、放棄される可能性が十分にありますから、負担と遺贈する財産とのバランスに注意するだけではなくて、その負担付遺贈が放棄された場合のことまで、しっかり考慮した上で、遺言書の内容を決定する必要があります。
遺言書作成の注意点 その4 遺言書の保管場所は悩ましい問題です
遺言書の保管場所については、一概に、「ここに保管すれば安心」ということをアドバイスすることができず、悩ましい問題です。
遺言の方式によって、遺言書の保管方法は違ってきますから、順に説明します。
公正証書遺言の保管について
公正証書遺言は、原本、正本、謄本の3通が作成され、原本が公証役場に保管されることになりますから、公正証書遺言は遺言の方式の中で、最も安全に保管されます。
公正証書遺言が完成すれば、遺言者に公正証書遺言の正本、謄本が渡されることになります。
そして、その遺言書に遺言執行者の指定がある場合は、正本を遺言執行者、謄本を遺言者が保管するケースが多いです。
また、遺言執行者の指定がない場合には、遺言書の正本を遺言者、謄本を相続人とすることもできますし、遺言書の正本、謄本ともに遺言者が保管することもできます。
このあたりは、遺言者の考え次第です。
自筆証書遺言・秘密証書遺言の保管について
自筆証書遺言・秘密証書遺言の保管について、特に法律に決まりがあるわけではありませんから、遺言者の自由な方法によって、遺言書を保管することになります。
自筆証書遺言・秘密証書遺言は、通常、遺言者自身が保管します。
そのため、遺言書が偽造・変造・隠匿される危険が常につきまといます。
遺言書の保管をあまりにも厳重に保管すれば、遺言者の死後、遺言書が発見されない場合が考えられ、その反対に、遺言書を誰かに発見されると遺言書が偽造・変造・隠匿されることにつながります。
このように、自筆証書遺言・秘密証書遺言の保管については、遺言書の保管方法が非常に悩ましい問題となりますから、遺言者の事情を考慮して、個別に検討するしかありません。
遺言書作成の注意点 その5 遺言書の検認は絶対必要!?5万円以下の過料
遺言書を自筆証書遺言・秘密証書遺言の方式を選択して作成した場合、検認手続きが必要になります。
検認手続きとは、家庭裁判所において、遺言書の存在を相続人に知らせて、遺言書の検認日における状態を確定する手続きです。
検認をすることで、後日、遺言書が偽造されたり、変造されたりすることを防ぎます。
検認を簡単に表現すれば、みんなで遺言書の状態をチェックするということです。
また、検認手続きが完了するまでに約1ヶ月程度かかります。
民法は、
「遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。」と規定し、さらに、
「遺言書を提出することを怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、又は家庭裁判所外においてその開封をした者は、5万円以下の過料に処する。」と規定しています。
なお、公正証書遺言を作成した場合は、検認手続きは不要となっています。