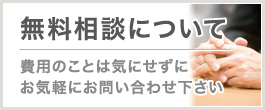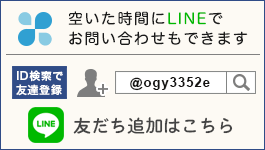遺言書の失敗例・無効になるケース
その1 公正証書遺言でも無効になる!? 証人になれない欠格者の存在
公正証書遺言であっても、見落としがちな無効原因、それは、証人の欠格事由です。
公正証書遺言の作成には、証人2人以上の立会いが必要とされています。
次の者が民法に規定されている証人になることができない者です。
- 未成年者
- 推定相続及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系卑属
- 公証人の配偶者、4親等内の親族、書記、及び使用人
これらの証人欠格者が、証人として、立ち会った公正証書遺言は無効になります。
一方、適切な証人2人以上の者が証人として立ち会い、そのほかに、証人欠格者が同席していた場合の遺言の効力については、原則として、有効であるとされています。
このようなことから、公正証書遺言の作成にあたっては、証人欠格者の立会いに十分な注意が必要です。
その2 なぜ、自筆証書遺言は無効になる可能性が高いのか
民法は、自筆証書遺言に関して、
「自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印をおさなければならない。」と規定しています。
自筆証書遺言を作成するために、最低限知っておくべき留意点は、次のとおりです。
- 遺言書の全文を自筆することが必要で、ワープロ・代筆は、遺言書が無効となります。
また、他者の添え手による補助も避けるべきです。 - 遺言書に日付を自書する必要がありますから、当然、日付の記載がない遺言書は無効です。
遺言書の日付は、遺言書の全文を記載した日付を記載します。
そのため、遺言書の作成は、出来る限り1日で完成させ、その日付を記載するべきです。
そして、日付は、具体的な日時で記載する必要があり、「○月吉日」という記載では、遺言書が無効となります。 - 遺言書に記載する氏名は、できるだけ戸籍上の氏名を使用します。
また、遺言書が複数枚にわたる場合でも、氏名の自書はそのうちの一枚で構いません。 - 遺言書の押印に用いる印は、できるだけ実印を使用します。
- 遺言書が複数枚にわたる場合には、連続した一通の遺言書であることを示すために、契印をすることが望ましい。
次に、自筆証書遺言の訂正方法に関して、民法は、
「自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を附記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印をおさなければ、その効力を生じない。」と規定しています。
自筆証書遺言は、すべて自筆で間違えることなく、記載することが求められますが、もし、全文を自筆する途中に文字を間違ってしまった場合には、民法の定める方式に従って、加除・訂正をすることになります。
自筆証書遺言の訂正の仕方は、次の通りです。
①削除する箇所を二重線で消し、その箇所に押印する
②正しい文言を記載する
③余白に訂正した箇所と訂正した文字数を付記し、署名をする
自筆証書遺言の加除・訂正に際しては、厳格な民法の方式に従うことが求められます。
民法の方式に従わない場合には、たとえ、加除・訂正をしたとしても、その加除・訂正はないものとして扱われます。
そのため、遺言書の内容に大幅な加除・訂正が必要になる場合には、再度、新しく遺言書を作成し直すことをお勧めします。
自筆証書遺言はトラブルが多く、方式不備で無効になる可能性が高い遺言書の方式ですから、自筆証書遺言を作成するためには、様々な法律知識が必要となります。
その3 代襲相続で大失敗!? なんとも難しい代襲相続
代襲相続とは、遺言者が死亡する前に、すでに一定の相続人が死亡・廃除・欠格によって相続権を失っている場合に、その相続人の有していた相続分と同じ割合の相続分を、代襲相続人に取得させる制度です。
代襲相続の典型例は、遺言者の孫が代襲相続人となるケースです。
それは、遺言者の子がすでに死亡・廃除・欠格によって相続権を失っている場合、その子の有していた相続分と同じ割合の相続分を孫が取得するというケースです。
本来、孫は遺言者の相続人ではなく、相続権はありませんが、代襲相続制度によって、孫に相続権が与えられます。
代襲相続の制度を知っておかないと、代襲相続人を見落とした状態で遺言書を作成してしまう危険性があります。
代襲相続人を見落として財産を配分した場合、代襲相続人の遺留分を侵害している可能性が高いですから、遺言書によって、トラブルの火種を残してしまうことになります。
つまり、代襲相続制度を知らない場合、代襲相続人が相続権を取得することに気づかない状態で遺言書を作成してしまい、大失敗する可能性があるということです。
その4 まさか、遺留分減殺請求で遺言書が台無し!? その理由とは!?
遺留分制度とは、一定の相続人に最低限の相続財産を保障する制度です。
遺言者の立場からすると、遺留分権利者は配偶者・子または子の代襲相続人・直系尊属です。
遺留分権利者には最低限保証された相続分があることから、相続によって取得した相続財産が遺留分に満たない場合は、「遺留分を侵害された」として、侵害された遺留分を取り戻す遺留分減殺請求権があります。
そのため、遺言書を作成するにあたっては、遺留分権利者の遺留分を考慮して遺言書の内容を検討する必要があります。
もし、遺言書の内容が遺留分を侵害する場合、その遺留分を侵害された遺留分権利者から、遺留分減殺請求権が行使される可能性があるからです。
その遺留分減殺請求権が行使されるといった事態はそれまで仲の良かった相続人間の関係を壊してしまう危険性があります。
相続人のためを思って、遺言書を作成したのにも関わらず、その遺言書が遺留分を侵害する結果、思わぬ、事態が相続人間で発生してしまうことになります。
そのため、遺留分を侵害する遺言書を作成してしまうことのないように、遺留分権利者が有する遺留分には十分注意する必要があります。
その5 遺言書作成の意外な落とし穴、遺産分割協議が必要!?
遺言書によって、相続財産の全部について、それぞれの財産を誰に相続させるのかが定められている場合には、遺言者が亡くなり、相続が開始した後、遺産分割協議は必要ありません。
なぜなら、全ての財産について誰が相続するのかが決まっているからです。
それに対して、相続財産の全部について、それぞれの財産を誰に相続させるのかが定められていない場合には、遺言者が亡くなり、相続が開始した後、遺産分割協議が必要となります。
なぜなら、誰が相続するのかが決まっていない財産があるからです。
例えば、遺言書を作成する目的が、相続人間の仲が悪い場合であるなど、何らかの理由により、遺産分割協議をする余地を無くし、相続人間の遺産分割協議でのトラブルを防ぐことにあるなら、単に遺言書を作成すれば良いわけではなく、相続財産の全部について、それぞれの財産を誰に相続させるのかを定め、遺産分割協議の余地をなくす遺言書を作成することが必要となります。
このように、遺言者にとって最適な遺言書を作成するためには、遺言書作成の最後の段階で、その遺言書で本当に遺言者の希望する目的を達成することができるのかを確認することが必要になります。